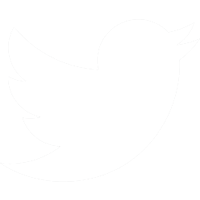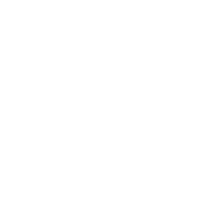職人インタビュー
HOME > 職人インタビュー > 京うちわ 饗庭智之氏

必然性をたどっていったら、答えが見えてくるみたいなところはありますね。

七代目から専門店として、
うちわを扱うようになられたとお聞きしました。
元々は滋賀県の饗庭(あいば)村の出だと聞いています。
雪深い地域で、竹がよく生えている所だったようです。竹がよく取れる地域から出てきて、竹製品を作って、竹に関わる商売をする。ロングスパンで考えてみれば自然な流れで、必然性をたどっていったら、答えが見えてくるみたいなところはありますね。
御所うちわが起源にあるといわれている、
京うちわの歴史について教えていただけますか。
京うちわが成立するのは、江戸時代ぐらいだといわれています。
南北朝時代に出雲を通じて大陸と交流があり、頭は頭、把手は把手のセパレートタイプのうちわが入ってきたそうです。それが宮中で使われていたところに、土佐藩や狩野派といった絵師が入ってきた。御所の調度品などに彩色が加えられていくにつれ、そこにあったうちわにも彩色がなされて、民衆が「御所うちわ」と呼び始めたといわれています。
京うちわの魅力を伝える上で、どういった点に気を配られていますか。
僕は、うちわというアイテムを先祖から、また皆様からお預かりしている、
というふうに思っています。うちわの魅力をどうやって伝えていけばいいのか常に考えていますが、最も大切なのは出番を増やすこと……
つまり、使ってもらい、見てもらう機会を増やすことで、うちわの文化・魅力を広く伝えていきたいと思っています。
どのような経緯で飾りうちわは誕生したのですか。
実は、先代と先々代は小売りをしていませんでした。
自分のブランディングを押し出すよりも、スポンサーのご依頼通りのものを作っていれば一応食べていけたからです。時期的には高度成長期の流れの中で、電化製品もどんどん普及してきた頃でした。
そんな中で、少し作家志向に走り、「目で涼をとる」といって、ばちーんと透かしてしまったんです。僕自身、「ああ、そういうことか」と納得できたのは、ここ数年のことですね。
親父は「継いでくれ」とは言いませんでしたけど、職人たちからはやっぱり「次は頼むぞ」と言われて育ちました。

幼い頃から職人の皆様のお仕事ぶりを間近に見てお育ちになった、
とうかがっています。この道へは自然な流れで入られたのですか。
幼い頃の僕のキャッチボールの相手は、親父ではなくて職人やったんですよ。
また、どこかへうちわをお届けする時に「おう、乗っていくか」と声をかけられて“ドライブ”に連れて行ってもらったりもしましたね。今と違って、職人は従業員としてだけではなく、家のことも仕事をしてくれていました。親父は「継いでくれ」とは言いませんでしたけど、職人たちからはやっぱり「次は頼むぞ」と言われて育ちました。
職人の修行というのはどのようなことから始められたのですか。
基本は“見て覚え”ですね。
体育会系のグラウンドの中に放り込まれるというような感じでしょうか。はじめは完全に撥ねつけられているというような感覚がありましたから、自分がしたいと思うことがあっても、一応口には出すんですけど「あほか」と一蹴されてしまいます。ですので、みんなが帰ってから夜中に練習するわけです。できないのはわかっているんですが、3分の1でも4分の1でもやっておくと、次の日の朝、職人が見て「しょうがない、つきあったろか」と。
そんな繰り返しでしたね。

伝統工芸品のありかたは、
ライフスタイルによって変わってきていると思います。
京うちわ専門店としてお感じになられていることはありますか。
古くからいわれてきた“これが正解”みたいな常識は、やっぱりわからないじゃないですか。でも、自分が判断するものでもなくて、結局は何を希望されているのか、ということですよね。職人というのは、望まれたイメージを具体的な形にしてさしあげるという職業、という言い方もできます。ですから、お使いになる方が望まれているイメージをこちらが実現していくということがもっと必要だと感じます。
最近のお仕事内容の傾向はどのように変化されましたか。
どんどん住まいの環境が変わってきていますよね。それに応じて、こちらも少しずつ変化していくわけです。少し前までのマンションですと、玄関の戸を開ければ必ず靴箱があって、物を置くスペースがありました。しかし最近は壁面収納になって、ずいぶん様相が変わりましたね。「ではどうしたらいいのだろう」「壁に掛けられるようにしようか」という。他にも、うちわは和のものだから和室のあしらいにと思われる方が多いですけど、マンションのエントランスだったらこんな感じであしらったらどうだろうとか色々と考えています。
千本張ろうが、五千本張ろうが、同じコンディションで次々に張っていける状態を常にキープしていくのが職人です。

京うちわの制作工程のポイントについて教えてください。
ポイントは「仮張り」ですね。
本番の紙に張り替える前、仮張り用の捨ててしまう紙に骨を1本1本張っていくという作業です。まっすぐにしゃんとした面を保持したうちわを作るために大切な作業で、障子や襖と同じ張り方をしています。
強い糊で無理に定着されるとひずみができてしまいますので、水で薄めた弱い糊でつけていきます。糊板に糊を敷いて、骨を伏せることで均一に糊がつくのですが、あとは置いたらひっつくだけ、というところまでに至るベース作りが難しいんです。

全工程の中で「仮張り」はやはり一番難しい部分といえますか。
仮張りはとても細かい作業なので、ご覧になる方は「すごいな」とおっしゃってくださいますが、この作業自体が難しいというよりも、本当に難しいのは同じコンディションで仕上げることなんです。
千本張ろうが、五千本張ろうが、同じコンディションで次々に張っていける状態を常にキープしていくのが職人です。骨に糊を付けるという工程においても、糊板は木製なので最初は水分を吸い込んでしまいます。また、時間の経過によっても糊が濃くなっていきますので、そんな中で常に一定を保つということが難しいところです。

京うちわ作りの素材選定の決め手について、
教えていただけますか。
うちわ作りの素材は丹波の真竹と、越前の紙を使っています。
竹などの芯になるものは、自分が納得できるものでなければ始まりません。
紙の場合はやっぱり「ある程度調湿ができる」ということでしょうか。これが決め手の一つといえるでしょうね。
といっても、素材選定の決め手はこちらが採用していることであって、お客様が喜ばれるのであれば何を使ってもいいんですよね。ご要望ということであれば何でも使います。
「もともとあったような専門家を養成できるほどに、業界が充実していかなあかん」というのは、究極の目標としてあります。

後継者不足の問題から、
社内に職人を抱えて育成されるようになったそうですね。
色々なものができなくなってきた時、僕らの判断は三つあります。
一つめは、人間ごと作ってきっちりやれるようにしていくこと。二つめは、今あるものを流用していくこと。そして三つめは、品格が伴わないくらいならカッコ悪いから仕事をやめてしまうということ。 できれば二をしながら一にいきたいのですが、細かい部分についてはそこまでいけないこともたくさん出てきます。それよりもやっぱり、うちわ文化を広めて、お使いいただく活動を増やして、「もともとあったような専門家を養成できるほどに業界が充実していかなあかん」ということが究極の目標としてあります。
今後、どのような作品に挑戦したいとお考えですか。
自分で考えないものにしたいと思いますね(笑)
やっぱり人間一人のなせるもんなんてたかが知れてます。それはそれとして、ブランドの中で自分のできる範囲は狭いですけど、もっとお使いになる方のご意向を承って、後は自由に楽しく、その人が扱いやすいように、その人が売りやすいように、その人がしやすいようにということを、うちのできる範囲内でできればと思います。
最後に、饗庭さまにとって「京うちわ」とは何か、
ずばり一言でお願いします。
僕にとって、僕そのものですね。
なんというか、もう浸かりきっちゃってますね(笑)
(平成25年5月)
プロフィール

京うちわ 阿以波
元禄二年(西暦1689年)創業初代長兵衛が近江の国の“饗庭(あいば)”より、都に出て店をひらいたことに始まります。 七代目よりうちわ専門店となり、御所うちわの伝統を伝える「京うちわ」を作り続けてきました。 現当主は、その十代目。『阿以波』のみとなった京うちわの製作技術を今に伝えるとともに、新たな「うちわ文化」を創造し続けています。